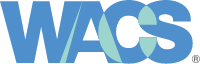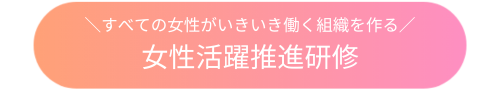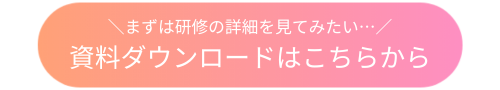日本の女性管理職の比率は?管理職が増えない理由と企業が実施すべき施策

社会が多様化し、これまで見過ごされてきた社会の矛盾やジェンダーギャップ克服のためのさまざまな取り組みが行われています。このようなダイバーシティの代表例として、女性管理職比率の改善がありますが、政府が定める目標に対して、女性管理職の比率はまだまだ足りていないのが現状です。そこで今回は、女性管理職比率の現状のほか、改善が進まない理由や企業が実施すべき施策についてご紹介します。
女性管理職の比率の現状は?
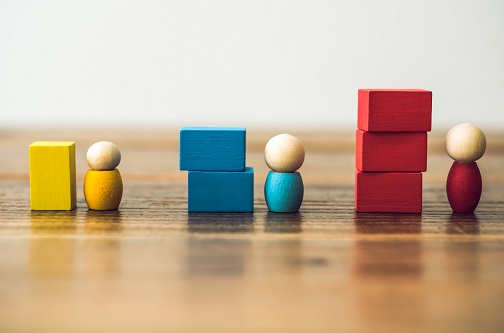
日本の女性管理職比率の現状
まずは、日本の女性管理職比率の現状についてご紹介します。政府は、「2030年までに女性の管理職比率を30%以上にすること」を目標に掲げていますが、2022年の政府調査によると、係長級が24.1%、課長級が13.9%、部長級が8.2%と目標を大きく下回っているのが現状です。2022年以前と比べて右肩上がりにはなっていますが、目標達成のためにはまだまだ課題が多く残されています。
海外の女性管理職比率は?
国内と国外の女性管理職比率を比べると、日本が海外から大きく遅れをとっている現状も見えてきます。
2022年国別の女性管理職の割合を見てみると、比率が高い順にスウェーデン41.7%、アメリカ41%、シンガポール40.3%となっており、日本が目標とする30%を大きく上回っています。対して、日本の女性管理職割合は12.7%にとどまっており、国際的に見ても女性管理職比率が低い国になっています。
出典:男女共同参画局 男女共同参画白書(令和5年版)
出典:労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2024」各国別の女性管理職の割合の国際比較
女性管理職の比率が増えない理由

なぜ日本は女性管理職の比率が増えないのでしょうか?女性管理職の比率が改善されにくい理由として、以下のような原因があると考えられます。
管理職の業務負担がまだまだ大きい
管理職は業務負担が大きく、労働時間が長くなりやすいというイメージがまだまだ根付いています。産休・育休・時短勤務などの制度を導入している企業が増えているものの、このような管理職のネガティブなイメージはなくなっていないといえるでしょう。
女性が働きやすい環境がまだ整っていない
働きやすさを重視した制度の導入などは進んでいるものの、取得者がまだまだ少ない、運用が上手く進んでいないという企業が一定数あります。子育て支援が充実していないケースもあり、企業側のさらなる環境整備が必要だといえるでしょう。
産休・育休で昇進が遅れやすい
産休・育休を取得すると、その間にキャリアが中断されることになります。これが女性の昇進機会を制限し、管理職へのステップが遠のく原因のひとつになっています。また、キャリアが途切れない男性と比べて、産休・育休を取る女性が競争で不利になりやすいのも現状です。このような、ライフステージの変化による不平等が起こりにくいような制度設計が必要といえるでしょう。
女性の管理職意向がまだ低い
日本では、「管理職は男性がなるもの」といったイメージが根強く残っています。ご紹介したような制度が不十分なことと相まって、管理職になることにためらいを感じる女性も少なくありません。制度によって、産休・育休による不平等をなくすほか、昇進後の支援を充実させるなど、女性が「管理職になりたい」と思いやすいような体制を整える必要があります。
女性管理職の比率を高めるメリットは?

女性管理職の比率向上は、企業にさまざまなメリットをもたらします。女性管理職を増やすことで、どのような効果が見込めるのかもおさらいしておきましょう。
ダイバーシティが促進されイノベーションが生まれやすくなる
女性管理職が増えることで、多様な視点やアイデアが職場にもたらされ、組織のダイバーシティが促進されます。男性中心だった企業の中核に女性が参加していくことで、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなり、より消費者の多様なニーズに対応しやすくなるでしょう。
人材流出を防げる
女性が働きやすい環境や昇進のチャンスがある企業は、社員が長期的に働きやすくなるため、人材流出を防ぐ効果が期待できます。特に、管理職に女性がいると、女性社員も将来のキャリアパスが見えやすくなり、企業への信頼や愛着が増します。また、男女問わず、ダイバーシティを重視する企業文化は働きがいを高め、離職率の低下につながるとされています。
社員のモチベーションを高める効果がある
女性管理職の存在は、社員全体にとって「性別やバックグラウンドに関係なく公平に昇進できる環境がある」といったメッセージになりえます。男女問わず、すべての社員が能力や努力次第で昇進できる環境が整っていることは、働く意欲やパフォーマンスに良い影響を与えるといえるでしょう。
企業の評価が高まり優秀な人材を獲得しやすくなる
女性管理職の比率が高い企業は、社会からの評価も高まります。特に、ジェンダー平等に関心が高まっている今日では、多様性を重視する企業に魅力を感じる優秀な人材も増えています。企業の評価が高まると、求人応募者の質が向上し、業界内での競争力も増します。また、社会的責任(CSR)を意識する企業としてのブランド価値も上がり、企業全体のイメージアップにもつながります。
女性管理職の比率増に!企業が実施したい施策

最後に、女性の管理職比率を向上させるために必要な施策についてご紹介します。
女性管理職を外部から採用する
外部から女性管理職を採用することで、企業に新しい視点や経験が加わり、社内のダイバーシティが向上します。また、外部からの採用は、すでに管理職としての経験を持つ人材が即戦力として活躍できるため、管理職の育成に時間がかかる、といった問題も解消できます。
評価制度を見直す(時短・育休でも昇進できる制度に)
時短勤務や育休・産休を取得した女性が昇進しにくい状態を改善するためには、評価制度の見直しが不可欠です。仕事の量や働いた時間だけでなく、成果や実績を評価基準に加えることで、柔軟な働き方をしながらもキャリアアップが目指せる環境に整えられる可能性があります。
ロールモデルの女性管理職を育成する
身近に成功している女性管理職がいると、ほかの女性社員も管理職としての将来をイメージしやすくなります。また、ロールモデルとなる女性管理職が実際に活躍することで、社内の風土が「誰でも平等に管理職になれる」という意識に変わり、組織全体のモチベーションも向上するでしょう。「即戦力の女性管理職を外部から採用する」と合わせて、ロールモデルの育成にも取り組むことをおすすめします。
女性のキャリアに特化した研修プログラムを導入
「女性社員の管理職の昇進意欲を高める」「女性がキャリアアップしやすい職場には何が必要なのかを学ぶ」など、女性社員や経営陣を対象とした研修プログラムを受けることも重要です。スキル・キャリアアップの意欲がある女性社員のモチベーションをさらに高める、キャリアアップを目指す女性が働きやすい環境を整備するという2つのアクションへの効果が期待できるので、女性の管理職比率に課題を感じている企業はぜひ検討してみてください。
【ワコールキャリアサービスの女性活躍推進研修】
女性活躍推進研修は、総合人材サービス会社として、創業より多くの働く女性と向き合い、寄り添ってきたワコールキャリアサービスだからこそできた「女性の為の研修プログラム」です。
キャリアを考える当事者本人へのメンタルサポートだけではなく、周囲の環境にもアプローチできるのが特徴。それぞれの分野に精通した講師たちによる、企業・女性の悩みを解決するプログラムを提供しているので、女性活躍に課題を抱えている企業は、ぜひ以下のリンクから詳しい内容を確認してみてください。
まとめ
日本の女性管理職比率は、2022年の時点で12.7%と、諸外国に比べてまだまだ低いのが現状です。「女性管理職の比率を高めたいけど、何をしていいのかわからない」「制度の導入などは進んでいるが、女性管理職が思ったように増えない」という企業は、ぜひ今回ご紹介した、外部採用・ロールモデルの育成のほか、研修プログラムの導入を検討してみてください。